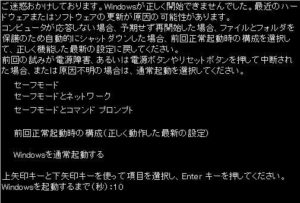Twitter等で続くアルバイトの投稿炎上事件。その予防と対策
こんにちは、平山です。

相次ぐTwitter”炎上”事件。企業ブランドが1人の店員の行動で危機に
最近、アルバイトの若者がTwitter等で不衛生的な行動を投稿して、大手飲食チェーンやスーパーなどが対応に追われるという事件が続いています。
参考記事)
- 「ピザハット」店員が、生地を顔に貼り付けて遊ぶ
- 蕎麦屋「泰尚」バイトが、厨房の洗浄機やシンクに足を突っ込む(※記事削除されたようです)
- ステーキハウス「ブロンコビリー」スタッフが冷凍庫に入って遊ぶ(※記事削除されたようです)
- 「丸源ラーメン」スタッフ、食材をくわえた写真を投稿。窃盗の告白も(※記事削除されたようです)
- 「ほっともっと」店員、冷蔵庫で寝る(※記事削除されたようです)
- 「バーガーキング」店員、食材に寝そべる(※記事削除されたようです)
- 「ローソン」アイスクリームケースに従業員が入り込む(※記事削除されたようです)
それぞれの企業が、謝罪文をWebで掲載したり、該当社員を解雇したり、場合によっては店舗閉鎖、損害賠償請求など、大騒ぎに発展しているケースもあります。これらはネットニュースで流行のように取り上げられました。
しかし、こういった騒ぎは今に限った事ではなく、以前からありました。例えば、3年前に吉野屋のアルバイトが食材で遊んでいる風景を動画サイトに投稿した「テラ豚丼」事件がなどが知られています。
当時はニコニコ動画などの動画サイト、今回はTwitterに場を移した訳ですが、今後も使うツールが変わるだけで、こういったネットを使った”事件”は起こり続けるでしょう。
日本を含む世界で広がる現象。ネット社会は1人が大きな影響力を持つ。
こういった騒ぎは、日本だけではありません。数年前から、アメリカ始め世界中でこういった"炎上"事件は発生しており、問題化しています。むしろ日本は、その国民性のおかげか、まだ「おとなしい」方と言えます。
アメリカでは飲食店の店員が唾や排泄物を商品に混入してその写真を投稿するなど、「本気で洒落にならない」過激なケースも発生しています。このまま騒ぎが加熱していけば、日本でもそういった強烈なイメージダウンに繋がる事件が起きるかもしれません。
参考記事)
・アルバイトの悪ふざけ写真投稿、米国でも起こっていた(※記事削除されたようです)
・最近話題の悪ふざけ写真投稿、アメリカでも起こっていた(※記事削除されたようです)※下品・不潔・不快な写真が含まれています。ご注意下さい。
予防の為には「アメ」と「ムチ」その両方の周知徹底が必要。
こういった事件を防ぐために、経営者はどうすればいいでしょうか。
私はアメとムチ、双方の対策が必要だと考えます。つまり「ES(従業員満足)の向上」と、「監視・罰則の強化」です。どちらかだけでは、上手くいきません。対応が甘すぎればスタッフは環境に甘えてしまいますし、厳しいだけでは、スタッフはストレスから「腹いせ」に走りかねません。どちらにも偏り過ぎず、うまくバランスを取ることが肝要です。
ES向上の例
- やりがいの持てる昇級/昇給制度を設ける
- よく褒めることで、スタッフの自己承認欲求を満足させる
- 接客教育にコストを掛け、仕事にプライドを持つ人材に育てる
- 愛着の持てる職場環境の整備や、福利厚生の充実
監視罰則の強化例
- 携帯/スマートフォンの職場への持込み禁止
- 採用時のSNS利用調査
- 雇用契約の見直し
- 社内LANでのアクセス制限、監視
これらを上手く結びつけ「きちんと職場のルールを守ることでスタッフが褒められたり昇給する」「職場の無線LANを使わせてあげる代わりに、SNSには繋がらないようにする」などの仕組み作りが重要です。反対に、一線を超えてしまった場合は大変なことになる、と知らしめておくことも必要です。
突き詰めていくと、スタッフを使い捨てにせず、愛情を持って教育していく、という事にも繋がるのではないでしょうか。ちょっと飛躍かもしれませんが、一連の事件は、企業のブラック化、若者の雇用情勢悪化とも無関係ではないと、私は考えています。所属組織への愛情が育っていれば、一連の事件は防げたかもしれないと、私は考えます。
まずは現場指導者の育成を。
これらの教育や改善は、日常的、恒常的に行われるべきものです。トップダウンで通達したからといって、簡単に浸透するものではありません。現場レベルでの努力の継続が必要です。その為には、現場指導者の教育、質の向上が不可欠です。彼らには、スタッフの採用、教育、SNS、そういった複合的な知識と裁量が求められます。優秀な人材をゲットするには、待遇も上げる必要もあるかもしれません。
余談ですが、管理コスト削減のため、店長を全て非正規雇用にすると発表し、その同時期に炎上事件を発生させた「丸亀製麺」が、それを逆説的に証明する例かと思います。サービス業の企業が人事コストを下げすぎると、かえって全社的な被害に繋がる可能性もありえます。
参考)
・丸亀製麺 全店舗をパート店長に、地元の人材起用(※記事削除されたようです)
・丸亀製麺 ざるのカビ発生問題で運営会社社長が陳謝 4月上旬に客から指摘(※記事削除されたようです)
実際に起きてしまったら。早さと真剣さがポイント。
こういったマイナス情報の拡散スピードは爆発的です。企業のPR情報を広めるには多大な労力が必要ですが、負の情報はあっという間に広がります。そして、SNS拡散の常ですが、お祭り騒ぎはあっという間に終息してしまいます。
つまり、企業の対応が早ければ、その負の情報とセットで広められる事で、事態の収拾も早くなりますが、対応が遅いと最初に広まったマイナスイメージだけが消費者に印象として残ってしまい、その後の企業発表などは存在すら知ってもらえない、ということです。
また、消費者もこういった騒ぎに慣れてきているので、「反省しています。今後の改善に生かします」という定型の謝罪文を掲載するだけでは、なかなかイメージ回復には貢献しません。口だけ、と取られてしまうのです。
正式な文書で伝える事も重要ではありますが、真剣さ、本気度を伝えるための内容や情報を流す必要があります。例えば、具体的な今後への改善内容や、犯人への罰則を発表することで、「もう安心です」と分かりやすく伝えることが肝心です。
アメリカで成功した事例としては、会社のトップが、悪ふざけ動画が投稿されたのと同じYoutubeで消費者向けメッセージを流した所、かなりのイメージ回復になったというアンケート結果があります。ネットユーザーに「真剣さ」を上手く伝えられた例です。
参考)米国ドミノ・ピザ炎上事件のその後-ブランド失墜の危機をソーシャルビデオが救った
※ビデオを流す前と流した後でのアンケート結果がまとめられています
最後に
世界の大きな流れとして、マスメディアなどの大企業・大組織による情報発信より、個人間での情報のやり取りが増しています。
平たく言えば、消費者がテレビを見る・雑誌を読む時間より、スマートフォン、SNSに触れている時間が増えています。実際、企業は広報の場を徐々にWebやSNS等に移行し、それぞれの業界の広告売上という形で反映してきています。
その際に見落としてはならないのが、大きな組織でもなく何のバックもない顧客やスタッフなどの個人に”力”が移ってきている、ということです。それ故、消費者を大事にしない、スタッフを大事にしない、拝金主義の企業は生き残れない時代になってきています。相手が多すぎる為に、何かあった時に、お金や強引な手法だけでは、対応仕切れないわけですね。
私は多少の混乱はありますが、この傾向自体は良い事だと思います。一昔前なら隠れたままだった悪や不都合が、見えるようになっているわけですから。知らぬが仏とは言いますが、どんな事実も、知らずにいるよりは、知って納得したいタイプですので。多くの消費者も、同じように考えるのではないでしょうか。